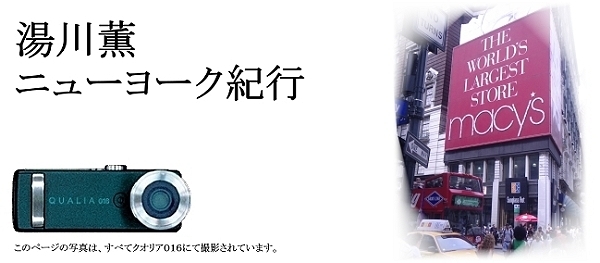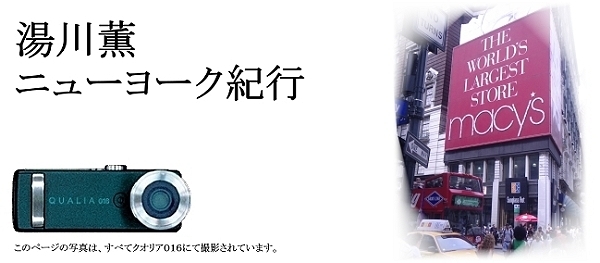|
ブラックアウトを(奇跡的に?)無事にやり過ごして、土曜日は、セントラルパークを散策。
ボートハウスでゆっくりとブランチを愉しんだ。
公園の景色もいいでしょ?
 
メトロポリタンに行ったら、さすがにブラックアウトの影響が出たのか、閉まっていた。観光客も美術館の前の階段にへたり込んでいた。(オレは余裕があるので、へたり込んだりはせんよ、わっはっは)
 
そういえば、泊まっているホテルの内部の写真を掲載していませんでしたね?
コレです。

綺麗でしょ。
素晴らしいホテルである。点数をつけるなら100点満点で100点である。実に快適で、ハードもソフトも、きわめて満足度が高い。
ふーん、NYにも、こんなにいいホテルがあったんだぁ。全室60という小規模なブティックホテルだが、アットホームな雰囲気で、ホテルフリークのオレがこれまでに泊まったホテルの中でも一、二を争う。それくらい良い。優秀。親切。リラックスできる。
え? ホテルの名前は?
ふふふ、あまりにも良いホテルなので、教えてあげないよーだ。(意地悪湯川)
ここはオレだけの秘密のNYの隠れ家にするのだ。
次回もここに泊まることに決めた。
などといっているうちに、やはり、ホテルフリークの性(さが)というべきか、一ヶ所では物足りないので、話題の(?)ロイアルトンにも泊まってみた。
いや、正確には、泊まらなかった。どういうことか、のちほど判明するはず。
まず、素人ホテル評論家のオレからいわせてもらおう。
これは「ホテルではなーい」。
ここには「泊まってはいけなーい」。
ここを褒めている奴は、嘘つきか、さもなくば目が節穴である。(あるいは両方)
まさに開いた口がふさがらなーい。
ダメダメだ!
非常に期待が大きかったせいか、あまりのハードとソフトのお粗末さに・・・言葉がみつからないよ、もう。
まず、話題の廊下だが、どうやら擦りきれておる。(とても美しく長い廊下で、その上を歩くだけで、緊張してしまうのだと。けっ)
次に、200室もあるホテルのくせに、受付にはふたりしかおらず、チェックインは長蛇の列。
オレがチェックインを済ませて、部屋に上がろうとエレベーターの前まで歩いてゆくと、ボーイが手につばをつけて、もらったチップを数えてやがる。オレのことをチラリと見るなり、
「ボタンはそこだ」(The button is there)
だと。
バカヤロウ。
おまえはチップを数える間があったら、客のオレのためにエレベーターのボタンくらい押せよ。なんなんだ、おまえは。しゃべる札束数え機か?
6階に上がって、極度に狭く、やけに暗い廊下を歩いてゆくと、オレの部屋が見えてきた。扉を開けて、中に入った。荷物をテーブルの上においたとたんにオレの眉間に皴が寄った。なぜか。
理由 テーブルはしみだらけで傷だらけ
このホテルは、有名なデザイナーがデザインしたことが「売り」なのだ。その家具類が古くて汚くて・・・電灯の金属部分には美しい模様が・・・じゃなくて、錆びてるだけじゃん。人がバカにしてんのか。
風呂場に入ってみると、使い古しとしか思えないシャンプーが転がっておる。前の人が半分つかったやつ。テーブルの上のマッチも・・・使用済みだぜ。
テーブルの上に置いてあった「ホテル案内」は、コピー機でコピーしたものをホッチキスでとめただけで、しかも、前のホッチキスの穴があいていて、おまけに紙のはしっこが汚く折れている。

バカヤロウ。こんなこと、ケチってるんじゃねえ。一泊3万5千円もするんじゃないのか。これじゃ泥棒さんだろうが。おまけにツインの部屋なのにバスローブはひとつしかおいてない。
気分を取り直して、一階に降りて、ホテルの奥にあるレストランに行った。
「予約している・・・」
こちらがしゃべっているのに、店員は、電話を取っておしゃべりを始めた。応対が終わると、にっこりと笑って、
「本日は材料がないのでビュッフェになっています」
だと。
オレはなぁ、「44」というレストラン目当てに、ロイアルトンに泊まることにしたのだ。それが、いくら停電の後とはいえ、お子様ランチみたいなものを食べるわけにはいかんのだ。
「ビュッフェなんか嫌だ」
「そうですか、お好きに」
この点で、オレの怒りは絶頂に達した。受付に行って、
「オレは、わざわざ日本からお子様ランチを食べに来たのではにゃい。ちゃんとしたレストランを紹介してもらいたい」と文句を垂れた。
すると、受付嬢は、
「あら、この先に、123というおいしいレストランがあるわよ」
と言う。
「わかった。予約を入れてくれ」
「あら、ただ、行けばいいのよ」
「はぁ?」
この時点で、オレはキレた。
バカヤロウ。
客がレストランの予約をしてくれといったら、予約を入れるのがホテルの仕事なのだゾ。
ちなみに、律義なオレは、この後、123というレストランに行ってみたが、明らかにファミレスだった。
ちがうだろ。今日だけは、高級な「食」を味わいたいのだ。だから、ここに来たのだ。
で、完全にブチ切れたので、オレは、30分でチェックアウトすることにした。
ふ、こんな、やる気のない三流ホテルになんぞ泊まって、せっかくのNY旅行を台無しにしてたまるか。
「チェックアウトする」
「すみません、コンピューターが動かないので、のちほどファックスで請求書を送ります。番号を教えてください」
「(鎌倉の自宅の番号を言った)」
「明日の朝にファックスします」
「日本にか? オレは、今、ここにいるのだゾ。明日の朝、どうやって、日本の自宅でファックスを受け取ることができるのだ?」
「さぁ」
うーむ、経営者の顔が見て見たい。
最悪。
|