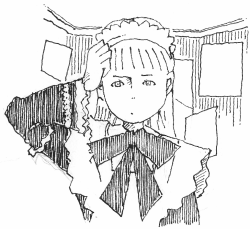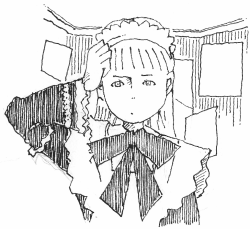|
|
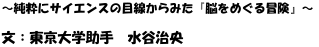
|
●第1章 ほむんくる
|
P16 1行目
中枢神経系における神経細胞の軸索の長さは数ミリメートル~1センチメートルくらいが平均的です。細胞体の直径が平均で10ミクロン程度ですので、それに比べれば、十分長い突起を伸ばしていることになります。中枢神経の軸索として最も長いのは、大脳皮質から脊髄まで伸びている錐体路の神経細胞でしょう(約50センチメートル)。また、1メートルにも及ぶ軸索は末梢神経系に相当し、脊髄から足の末端に伸びる運動神経繊維などになります。
|
P18 4行目
神経細胞の数は、大脳で数百億個、小脳で千億個あるといわれ、脳全体で千数百億個に及びます。たとえ一日に10万個の神経細胞が死滅したとしても、1年で3650万個、100年で36億5000万個がなくなる計算です。脳神経細胞の数を1500億個と見積もると、生涯で死滅する神経細胞の数は全体の2%程度になります。
ちなみに、脳卒中になると、たった1分間で虚血部位周辺の神経細胞が190万個死滅するという計算報告があります。これだと、発症後約20分で1年分の神経細胞を局所的に失うことになります。虚血発作後いかに早く医療措置が取れるかが、その後の人生を大きく左右することは想像に難くありません。
死滅した神経細胞が再生することはありませんが、海馬などの一部の領域で、神経細胞が新生することが明らかになりました。ソーク研究所の FredGage らのグループが1998年に、成人(検死体)の脳で新しい神経細胞が生まれていることを発見してから、神経再生の研究が注目を浴び始めました。また、胚性幹(ES)細胞がヒトから単離されたのも同じ1998年で、再生医療が急速に現実味を帯びてきたころでもあります。死んでしまった神経細胞とまったく同じ神経回路を蘇らせることはできませんが、それを代替させる機能を新しい神経細胞に持たせることができると期待されています。
http://www.nature.com/nm/journal/v4/n11/abs/nm1198_1313.html
http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/282/5391/1145
|
P23 最終行
実際のシナプス間隙(神経終末端と隣の神経細胞の間)は約20ナノメートルくらいです。それが2メートルくらいに見えるということは、カオルやアキラの身長は15ナノメートルくらいまで小さくなっています。ここで5ミリメートルの軸索の上を細胞体から神経終末まで歩いて行くとなると、約500キロメートルに相当する道のりを踏破してきたことになります。(ファンタジー小説なので、そんなことを考えてはいけません…。)
|
P24~26
神経伝達についての記述は何度も推敲して頂きましたが、小説として話を展開するためには、これが限界のようです。まず、神経伝達物質が開けることの出来る扉は、受け手の神経細胞(シナプス後細胞)の方にあります(∴P25のイラストは比喩的には正しい描写です)。神経伝達物質が神経終末端から放出されると、伝達物質が鍵の役割をして、シナプス後細胞にある扉(イオンチャンネル)を開けます。それに伴って、その開いた扉の中を電気信号が流れる(イオン電流)という仕組みになっているのです。
一方、神経終末端では開口放出により神経伝達物質がシナプス間隙に溢れ出ますが、このとき、物質が出て行く出口に相当する扉には鍵穴はついていません。終末端では、神経伝達物質を含んでいる小胞(シナプス小胞)が、細胞膜と融合し、融合孔が開口することで、伝達物質の放出を可能にしているのです。ここは扉が開くという表現より、穴があいたというイメージを思い描いていただいた方が妥当なように思います。したがって、終末側にある扉と、受け手側にある扉の性質はまったく異なることにご注意ください。
26ページの一行目で、カオルが「電気信号にならないと…」と言っていますが、その後の記述を正確に捉えると、カオル達は電気信号になるのと同時に神経伝達物質そのものにもなってしまっています。向こう側の神経細胞に渡るにはそういう記述をするしか方法はないので致し方ないでしょう。実際のシナプスでは、電気信号と化学シグナルは両立しません。細胞体から軸索を通って神経終末端まで届いた電気信号は、神経伝達物質という化学的シグナルに変換され、シナプス間隙を渡ったシナプス後細胞で、再び電気信号に変換されるのです。つまり、電気信号は間隙を伝っていくことはできないというわけです。このようなシナプスを「化学シナプス」といいます。
|